宇城道塾 2019年度 夏季合同合宿が開催されました
- jht900
- 2019年9月2日
- 読了時間: 18分
更新日:2019年9月10日
去る2019年8月31日(土)、9月1日(日)、宇城道塾夏季合同合宿が静岡県修善寺で行なわれました。
東京、大阪、仙台、熊本、岡山、名古屋の各クラスより、九州から北海道までおよそ70名が参加。
宇城塾長のもと、全国から志を同じくする仲間が集い寝食をともにし、2日間にわたる集中講義・実践を受講しました。
今回は、「宇城式呼吸法」と「サンチン」で、調和する身心を色々な応用検証を通して徹底的に学び、またそれを身体に染み込ませる実践が繰り返されました。
応用検証では、相手や周りと調和できた時の対立の全くない感覚を得ると、塾生たちから思わず感嘆の声が上がります。
調和する身体・統一体は、塾長に気を通してもらうほかに、各自の所作や呼吸法によってもつくられることを学びます。
この2日間、様々な実践検証の中で、呼吸法を繰り返し行ない身体に落とし込む機会をたくさんいただきました。
「最も大事なことは、『変化』することです。
変化は今という瞬間の時間の中にあります。
その瞬間の時間操作法の一つに呼吸法があります」
呼吸法の所作は丁寧に丁寧にすることが肝要です。呼吸法を行なう時の所作や手の動きががさつであると、身体に気が通らず調和も生まれません。
変化すなわち「できる未来」を自ら先取りし、かつ呼吸法にはさらにその上があることを塾長に示してもらうことで、呼吸法の一見単純な動作にも、毎回丁寧に取り組んでいくことで惰性にならずステップアップしていく。そういう心構えを植え付け、本質に向かう道筋を、塾長は示してくださいました。
― 「宇城式呼吸法」と「サンチン」の型を、2日間にわたって稽古 ―
(応用検証)
椅子に座って両足を押さえられる
→ 立ち上がることはできない
▼
→ 気を通されると簡単に立ち上がることができる 植物の根が固い土の間を探って伸びていくように
"すき間”ができ相手に入っていけるのだと言う
< 呼吸法での調和 >
呼吸法を行なって押すと、一列はすっと動く
ところがガッツポーズをしたり気合を入れたとたん
列は動かなくなる
全員が呼吸法での調和を実践
< 相手との間(ま)>
① 一人が一列先頭者から徐々に離れ、先頭者は「合った」と感じたところで合図する
② そこで第三者が列を押すと、簡単に崩れる。これが、間が合う、フォーカスが合った状態(調和)
③ そこから半歩でもずれると、列はまったく動かなくなる
この、間が合った一点から少しでも動くと切れてしまう課題への答えの一つとして、次のような検証が行われた。
① 一列との間が合ったところで、
② 離れたところにいる第三者を気遣い、歩み寄って声をかける
③ 間が合ったところから動いたにも関わらず、一列を押すと簡単に動く
< 調和力 >
十数人ががっちりと支えているが塾長にあっけなく崩されてしまう
塾長が「まったく力は使っていない」のが見て取れる
不思議としか言いようがないが、まさにこれが今の常識が非現実だ
ということの証しとも言える
< 人間の潜在力 >
両肩にそれぞれ4人ずつぶら下げて屈伸をする
→ 男性でも膝を曲げたところで動けなくなるか崩れてしまう
→ しかし、気を通されると女性でも簡単に屈伸し
さらには腕を広げて8人を弾き飛ばしてしまう
< 相手との調和 >
横になっている相手を起こす場合
→ 相手との調和がとれていると手を添えるだけで起き上がる
→ しかもこの時、相手は背中に乗られても何ともない程強くなっている
しかし、ただ引っ張るような場合
→ 相手は起き上がりにくく、かつ身体は弱くなっている
「宇城式呼吸法」の検証が教えてくれていること。
① すべてと調和する、すなわちそれは仲良くすること。
→ そのことによって潜在力が引き出されるということ。
② 調和の逆、すなわち自分さえという対立は人間力を劣化させていくということ。
講義と懇親会で途切れることのない学びの時間を過ごした塾生たちは、身心にエネルギーを充満させて、日常においての変化・成長を目指します。
宇城道塾 2019年夏季合同合宿記念写真
参加者の感想を紹介します。
●福島 公務員 51歳 男性 HO
熱く、深く、楽しく、希望に満ちた二日間でした!
凄く元気になりました!
8月下旬から9月上旬は繁忙期で、猫の手も借りたい状況なのですが、私に合宿を欠席するという選択肢はありません。
それは、この合宿に参加することでエネルギーをフル充填できることを身をもって知っているからです。
情けないことに、合宿参加前の私の身体の中はドロドロしたモノで一杯になっており、気持ちの悪いものを抱えたまま会場に向かったというのが正直なところです。
それが、宇城先生にお会いし、全国の塾生の皆さまの顔を見たとたん、ドロドロの嫌な感覚はどこかに消え去り、身体中が透き通った感覚になりました。
あとは、ご指導を通して、宇城先生のエネルギーがとめどもなく流れ込み、そのエネルギーが塾生の皆さまとの交流で増幅され、まるで生き返った気分です。
古来、人はこういったことを「ケガレ(気枯れ)」「ハレ」といった気の循環で回してきたとのだと思います。
しかし、現代社会はケガレしかない状況です。ハレの日は、ハロウィーンや何かのイベントで暴れるだけ。香港のデモが正しいのか否かわかりませんが、日本の若者にあのエネルギーがないことは確かです。
集団の人数を増やせば増やすほど、伝わる何かが増幅するという検証を体験しましたが、それは、導くもの、指導者の力と方向性によって、集団はどうとでもなってしまうのだということを強く感じました。
それは指導者の重要性、指導者が集団を成す一人一人の心を抱えられるか、それを正しく導けるかということだと思います。
私は合宿で、宇城先生の、全国の塾生の心をいただきました。その心を、三島駅に置き忘れることなく、熱海や新横浜の駅でポロポロ落とすことなく、自宅まで持ち帰り、明日からの日常、仕事で活かしていきたいと思います。
宇城先生
全国の塾生の皆さん
本当にありがとうございました。
私はもっともっと前に進めます。
やれることを全力でやります。
もちろん楽しみながら。
それがエネルギーです。
●兵庫 会社員 28歳 女性 NT
この度の合宿でも、本当に濃く、エネルギーに溢れた時間を過ごさせていただき、誠にありがとうございました。
呼吸、サンチン、その他さまざまなやり方で、エネルギーを取り込んで検証することを体感させていただきました。
印象に残っている検証の1つ目は、5人が1列に連なり、1人が列の先頭の人と向き合って少しずつ後ろに下がり、間がぴたりと合うと、5人の列が軽く押すだけで後ろに倒れるという検証です。間が合っている地点から少しでも動くと、5人の列とつながりが切れてしまいますが、困っている人を助けるために移動すると、つながりが切れずに調和したままでした。妨害しにくる人を投げることもできていました。しかし、助けようという気持ちだけで素通りしたり、困っている人がいない方に助けにいくつもりで走ったりしても、つながりは切れてしまいました。
どんなにエネルギーを保とう保とうと思って動いても、それは相手のない自分中心なことで、調和できずにエネルギーも保てないということ。しかし、困っている人の力になるような目標に向かって行動をしていくことで、周りと調和し、エネルギーを保って、周りから見守られながら、困難も乗り越えていけるのだということを体験させていただきました。また、気持ちがあるだけでもダメで、行動をしているつもりでもダメで、本当の現実の目標に向かって行動をしていかなくてはいけないと改めて気づかされました。
また、立った状態で曲げた両腕をそれぞれ男の方数名に押さえられ、腰を落とす・再び立ち上がる、を繰り返したり、その後、腕を左右にぱっと伸ばして腕を掴んでいた男の方の列を倒したりする検証もさせていただきました。どれも、自分の力では絶対にありえないことです。目の前に先生がいらっしゃるから、できるんだ、大丈夫だと、自然と思えて、動くことができました。
2日目の初めにも、先生を見たまま瞼を閉じると、正座の状態で上から押さえつけられていても、立ち上がることができるという検証をしました。
師という存在があるということ、信じるということ、それによって、自分では決して出せない力を出すことができるということを体験させていただきました。
たとえ、先生が目の前にいらっしゃらなくても、瞼を開けていても、日常のなかで先生を見続けられるように、自分の日々の改めてまいりたいと思います。
それから、丁寧に、丁寧にすることが大切だというお話も印象に残っております。呼吸も、丁寧に丁寧にとやる方が、強くなりました。私は、日常の中で、自分ががさつだと思うところがたくさんあります。呼吸を丁寧にして、仕事をはじめ日常の全ても、丁寧に行うように、自分を変えていきたいと思います。
そして、座っている人や寝ている人に手を添えて、立ち上がってもらう検証では、私はなかなか立ち上がってもらうことができませんでした。それは、自分が起こそう起こそうと意識して、手を引っ張ったり押し上げようとしたり、自分中心に動いてしまったからだと思います。自分中心ではいけないと頭で考えていても、実際には自分中心になっているということ、これも、日常のなかの自分のことだと思いました。全員で腕を組んで回るときも、隣の人と手が離れてしまうことがありました。これも、離してはいけない、という自分中心の意識が生まれるからだと気づかされました。
しかし、二人で手を繋ぎ、先生に気をかけていただいて、ものすごいスピードで回転したあとだと、何の抵抗もなく、座っている人を起こすことができました。そのときは、自分中心にどうこうしようという意識も、それではいけないという葛藤も、そもそも起こる暇がなく、その前に起こせてしまっているような感じでした。
自分にエネルギーがあるということが大事で、全ての始まりなのだと思いました。
そのエネルギーは、自分で頑張って作り出すものではなくて、正しい呼吸や型や行動をして、周りと調和することができたら、周りからいただけるものなのだと思いました。
まずは、呼吸を丁寧にすることでいただいたエネルギーをもって行動し、そのことによってもっとエネルギーをいただいて、そうすることで、自分をもっともっと変化させてまいりたいと思います。この度も誠にありがとうございました。
●東京 会社員 34歳 男性 OM
この度は合宿でのご指導大変ありがとうございました。合宿には数度参加させて頂いていますが、改めて、世界のどこにもない途方もない水準のご指導をいただいていることに驚嘆しながら体験させていただきました。
先生が仰る「下から上は見えない」のお言葉通り、先生がどれほど途方もない存在であるか、私には到底知ることができません。目の前でいとも簡単そうに再現くださることの全てが、日常では決して経験のできない貴重なものであることを噛み締めながら、学ばせていただきたいです。
集団に対して離れながら間合いを合わせ、そこから間合いの範囲を広げる体験は非常に勉強になり日常の大切さを痛切に感じました。生き方そのものが問われていると心底感じました。人々のエネルギーを抱えられる人になりたい、その上で「大丈夫ですか」の心で、弱い人に力を与える存在になる、そうすれば心無い妨害をはねのけて、幸せを実現できる。確固たる指針となりました。
変化したいという決意で参加させて頂きました。日常を変え、自らを変えます。ご指導ありがとうございました。
●東京 樹木医 53歳 女性 KM
宇城先生、このたびもとても楽しく学び多き合宿の時間をありがとうございました。また、先生のご指導を長年受けてこられた立派で温かい塾生の先輩方には、この度も温かくかつ的確な言葉をたくさんかけて頂きました。宇城先生に深く感謝しております。
以前は、せっかくの貴重な教えは忘れないようにしなくては、と思い、つい頭を働かせておりましたが、最近では、体がちゃんと知っている、理解していることを信頼して、頭で覚えようとせず、その場にいて体験することを楽しみながら時間を過ごせております。その方が実証もスムーズであることが理解できるようになりました。
懇親会の際、気を受け取った状態で、仲間と激しく動いているとき、手が離れないのがよい、とうかがい、うれしくなりました。今回は、どの実証もあまり簡単に手が外れず、けれど、外すまいと自分で頑張っているわけでもなく、そのような状態を楽しめました。少しずつですが、器の小さな自分の我が落とせつつあるのかな、とうれしく思います。最近では、できるできない、それ自体が問題なのではなく、それぞれの時の自分の動きや、かすかな心の状態などを観察してその違いを感じられるようになってきました。これも、宇城先生の達成度以上に成長のプロセス・方向性を大切にするご指導のたまものと感謝しております。
他にも呼吸法や型を丁寧に、丁寧にやる、というのを実際に何度もやって見せて頂き、その丁寧さ、厳密さに感銘を受けるとともに、今後の一人稽古の具体的な指針を得られたことを喜んでおります。心に残ることは他にもたくさんありますが、ここにはとても書き切れません。
私も教育に関わっておりますので、どの先生に指導を受けるのか、特に初期教育での先生の重要性は身にしみて感じております。私は道塾に縁を得て入れて頂き、宇城先生のご指導を受けられることを大変幸運に思っております。ここで頂いた幸せを周囲にも広げていけるようつとめます。今後ともご指導をよろしくお願いいたします。
●岡山 農業 33歳 男性 KT
今回も2日間、本当に本当に楽しい貴重な空間、時間を過ごさせて頂き、誠にありがとうございます。
たった2日間とは思えないほど濃い内容で、あまりに多くのことを学ばせて頂き、気づかせて頂き過ぎて、まだ頭の中では整理しきれず何を感想文に書いて良いのかまとまっていない状態ではありますが、今、パッと頭の中に思い浮かんだことを書かせて頂きたいと思います。
まずは、この2日間通してここまでじっくりと呼吸法とサンチンについて、様々な解説、検証をしながらご指導くださったこと、本当にありがとうございます。
今まで自分が行ってきた呼吸法やサンチンが、いかにガサツで、慣れから来る単なるエクササイズになっていて、何の意味もないことをやっていたのかと気づかされ、愕然としました。この合宿で気づかせて頂いたことを忘れず、一人でも深さを求める稽古ができるよう、日々丁寧に、丁寧に呼吸法とサンチンに取り組んでまいります。
また、今回は、特に、日常に生かせること、あるいは、日常で自分ができていないことに多く気づかせて頂いた合宿だったように感じました。私も中学生の頃、イジメにあい、クラスメートはともかく、教員からも見て見ぬ振りをされたことがあります。今思えば、その時の私は常に孤立していて、誰とも調和できていなかったのではないかと思います。そうなる大きな原因は家庭環境にもあったと思いますが、自分も大人になり、今度は自分が小さなことでも見て見ぬ振りをしてしまったことも多々あり、自分も人のことをどうこう言える資格はありません。しかし、今後は、自分だけではなく、自分の家族、子ども、将来の孫を守るためにも、今、自分が少しでも変わっていかなければと気持ちを新たにしました。そのために、人や社会や誰かのせいにして、そこと戦うのではなく、仲間、ファミリーとの絆を深める方向に全力を注いでいきたいと思いました。 今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。
●神奈川 パイロット 53歳 男性 TK
合宿では、呼吸法について、たくさんのご指導をいただきました。
その中で、所作の大切さについて学びがありました。
ほんの少し雑な動作になっただけで、呼吸法からくる本来の働きが失われます。
そして、丁寧な呼吸法を通じて調和する身体に変化することが実感できました。
調和した身体になった時、体が自由になります。
自由になった身体からは、なにか活力のようなものが生まれてきます。
また、身体が自由になった時には、頭の中もより自由になったような感じがします。
このような状態から何かを発想するとき、いつもの状態から発想するのとまったく違ったものになるのではないかと思います。
常に調和した身体で日常を生きていくことができれば、人生はずっと違ったものになるような気がします。 そして、そのように生きていくことが究極の目標であると感じます。 ありがとうございました。
●愛知 調律師 59歳 男性 FK
大変有意義で楽しい合宿に参加させて頂きありがとうございました。
毎回毎回パワーアップした合宿、いつまでもどこまでも進化され続けられる先生、常識外で想像を絶する講義、今回も参加させて頂き、今死んでも悔いのない高揚感で一杯です。
今回は特に、個人一人一人が呼吸法や相手を思いやる事によって先生に気を送って頂いた時と同じような統一体になる事が出来る練習を何度もさせて頂いたで、自信が少しずつ出来始めたことが凄く大きいと感じます。
それを、混沌とした現代に、なにか少しでも世の中を良い方向に修正出来る力に変換出来ればと思う次第です。
明日への活力にして頑張って行きます。
先生、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。
●三重 会社員 28歳 男性 SM
宇城先生、今回の合宿もご指導ありがとうございました。心身ともに解放されて非常に心地がよく、幸せで前向きな気持ちに包まれています。全国の塾生とともに先生に学ばせていただける道塾合宿は何にも代えがたい貴重な時間です。素晴らしい機会をいただき感謝申し上げます。
このたびの合宿では宇城式呼吸法をじっくりとご指導くださり、いくつもの検証を通じて身体の変化、調和と対立の差を感じる機会をいただきました。宇城式呼吸法は非常にシンプルな動きであるにもかかわらず、計り知れないエネルギーが詰まっており奥の深さに驚き感動しました。
特に、先生に合わせて全員で呼吸法をしたときの、全体の空気感がすうっと変わっていく瞬間は安らかで優しい気持ちになり身体全体が喜んでいる感じがしました。順序としては同じ動きであっても、雑にやったり、いままでの癖で力んでやると一気に空気感が変わり、時間が止まってしまうことも何度も繰り返し経験させてくださいました。
惰性で繰り返すことに意味はなく、奥の深さに向かって身体を変化させていくこと、ていねいに、ていねいに、がさつさ、横着さを少しでも減らしていくことを肝に銘じてまいります。きめの細やかさ、配慮を行きわたらせる心身の状態で生活するということがいかに大切なことか、理屈でなく身体の変化でご指導くださり、今日より明日、という希望、楽しみが大きくなりました。
統一体だと身体のあらゆる場所がエネルギーに満ちていることにも感動しました。
座ってペアの相手が自分の足を持ち上げる検証では、踏ん張る部分がないので、通常いとも簡単に足を持ち上げられてしまいますが、気が通った統一体だと全く上がらず、何の力をも入れずして相手を投げることができました。がっちりと足をつかまれていてもそんなことが気にならず、まったく問題にせずに気づけば相手が倒れていて、さらにその相手にも気が通っている状態で自然と笑みがこぼれます。
仕事や日常の人間関係の中で、いくら言葉で「調和」と唱えていても、自分自身のエネルギーが足りていなければ、かならずどこかでひずみが起こるのだと感じます。問題だと思っていたことが問題でなくなるスピード感、圧倒的なエネルギーで物事を乗り越えていく、というその道筋をまさに示してくださり、活力となりました。この感覚を身体に少しでも残し続けたいです。
2日間の合宿で本当に心身が元気になり、前向きに何事にも挑戦をしていく気概に満ちています。ていねいに、かつ勇気をもって日々歩んでいき、変化・成長していく自分にワクワクし続けたいと思いました。素晴らしい時間を本当にありがとうございました。
●福岡 自営業 44歳 女性 NF
大変貴重な二日間を本当に有難うございました。細胞と心は常に一体であること、まだまだ自分の認識のレベルが浅いことに改めて気付かせて頂きました。道塾合宿の参加は3回目でしたが合宿は普段の道塾とまた少し違い、心地よく、そして熱く、その空気感が大好きです。受講生の先生への思い、感謝がより溢れんばかりの方が集まるからかな、と感じながら、来れたことが大変有難かったし、それを理解してくれる家族や仕事仲間にも感謝です。
今回、呼吸法で数々の検証をさせていただきました。「間」の検証の時に「具合が悪い人を気遣う」ときは何方がやっても一番エネルギーがありました。人間の本当の強さはここ、と、こんなにわかりやすく体感させてもらい、間を取ってただ立っているのと行動に起こすことの大きな違いにハッとしながら、「今、変わる」「今、動く」しかない、「いつか、は退化」だと、自分の日常をリンクさせるとさらに気が引き締まる思いでした。孤高の先生が私たちに気付かせるためにここまでわかりやすい方法で、だけれど先生にしかできない、だからこうして降りてきてやってくださることがあり得ないですし、本当に凄い先生だなあ、と自分レベルの解釈でしかありませんが、そう思います。だからこの感謝を自己成長に変えなきゃ!と。
調和する穏やかさと厳しさの中の優しさをこの合宿で先生から十分に感じながら、先生の究極の強さと真の優しさに私たちがいかに守られていることかと思います。
呼吸法をご指導いただく中で「まだまだ皆は雑」とのお言葉は深く突き刺さりました。自分で意識してできるレベルと心の深さ・真心は全く別物であると諭されているような気がしました。ただやればいいのはもちろん違っても、心を込めようと思ってもやはり自分はそのつもり、でしかないこと、自分の過去の結果が今だから、早々できないことをしっかり受け止め、日々積み重ねながら、謙虚に自分と向き合っていきたい、と思いました。
会社で私がよく言葉にしていることに「今の自分の行動や思いがお客様にとっても、仕事仲間にとっても、お取引先にとっても、誰にとってもいいのかどうか、そうであれば自分にとっても結果必ずよくなる」と。これを自信をもって自分の仕事の経験を通して話せる事例が増えてきました。先生のおかげです。今後も行動し、経験を積んで、反省しながら後悔は無いよう進んでいきたいです。 貴重な2日間を本当に有難うございました。
◆2019年宇城道塾 受講申込受付中






















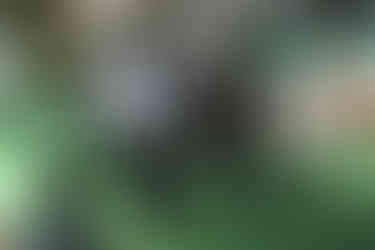































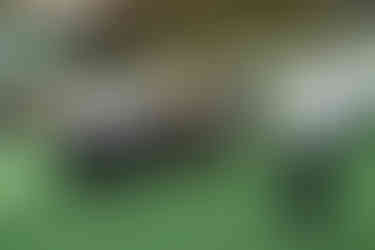









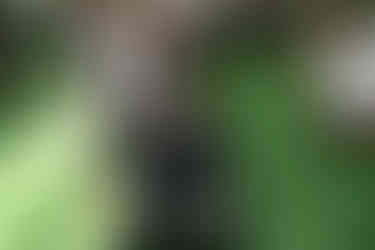





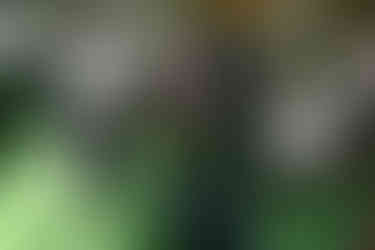



コメント